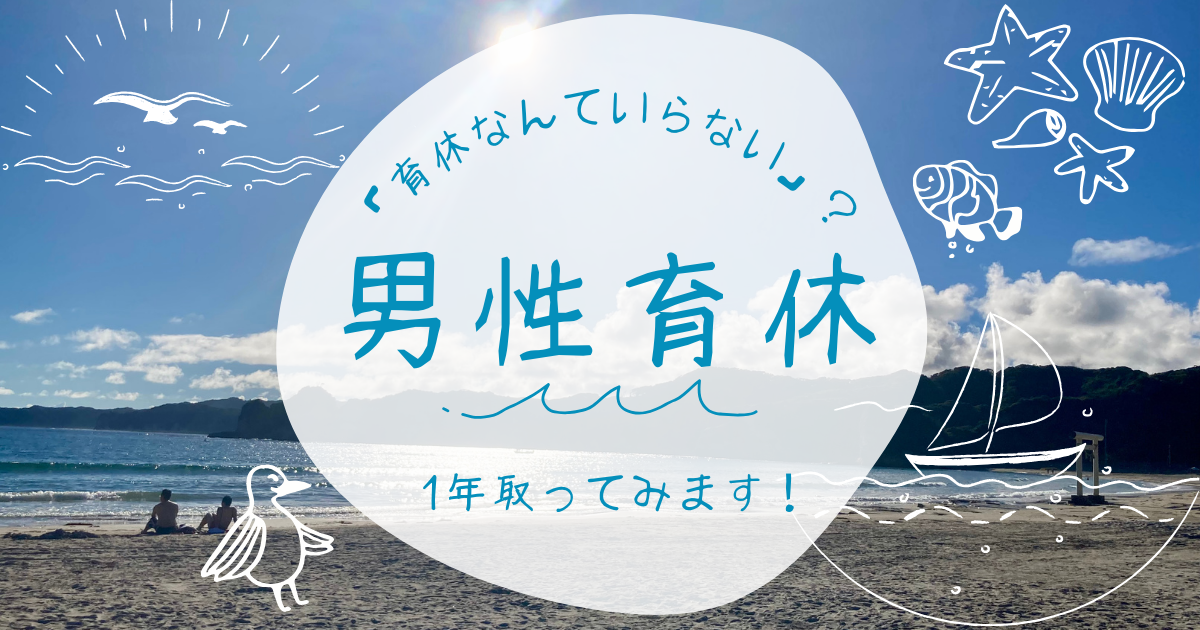夫目線で妻の妊娠について[選択的夫婦別姓編]松田青子著「自分で名付ける」を読んで
こんにちはトマト🍅です。
今回は松田青子さん著「自分で名付ける」という本を読んで、選択的夫婦別姓について考えてみました。
[なぜ夫婦は同姓?]
近年話題になっている「選択的夫婦別姓」のお話ですが、皆さんはどうお考えでしょうか。
名字問題2つ
①名字変更手続き問題
②アイデンティティ問題
・名字が変わると超めんどい!
いまだにアナログな手続き…
名字を変えることはたくさんの面倒事がついて回ります。まず身分証関連から銀行・カード・保険等の名字変更手続きが必要です。
これらの中には平日のみ対応のものもあるし、ネットでは変更できず書類を書いて郵送する必要があるものもあります。面倒ですよね。
平日の間それなりに時間が取られるものなので、名字変更手続きのために有休を取る必要があるかもしれません。
面倒ごとは職場でも…
そして職場でも名字が変わるのは面倒ですよね。そのままの名字で働いている人もいますが、社内ならまだしも取引先にまで名字の変更が周知されるには相当の時間がかかると思います。
僕も仕事で社外の方とやり取りをする時に、突然名字が変わっていたり、今の名字で検索すると昔の案件にたどり着けなかったりと困ったことが何度かあります。
我が家では、妻は名字にこだわりがありません(くるみはくるみだから名字はどちらでもいいという考えでした)。どっちの名字にするかはあまり議論にはならず、入籍する時はトマト🍅の名字に変えてもらいました。
くるみ🐿️が転職するタイミングで入籍して、次の職場ではトマト🍅の名字で働くと決めていたこともあり、職場を変える間の期間で手続きもあらかた終えることができました。
というかこの「名字変える手続き問題」が結婚を決める大きな要因となりました。結局会社側での手続きが間に合わず、旧姓で働くことになったんですけどね(笑)
・僕にとって名字とは
僕は名字が名前よりインパクト強めなので、基本的に名字で呼ばれることの方が多いタイプの人間です。(勝手に「名字型」と呼んでいます。逆はくるみ🐿️のような「名前型」。)
「名字型」の僕は名字を変えられるとイメージした時、自分が自分じゃなくなるというか、今までの自分とは違う人間になるというか、あまり肯定的なイメージは自分の中からは出てきませんでした。
「自分の名字が好き」というよりは「名字型」の僕は名字こそがアイデンティティ、といった感じかな。
もちろん男性が名字を変えたっていいんです。僕がこの問題に直面する可能性だってあったはず。たまたま「名前型」の人と結婚したから僕は名字を変えずに済んだのです。
とにかく、現代の日本で結婚を考える際には避けて通れない話題が名字の問題なのではないかと思うのです。
・名字について考えたきっかけ
僕が名字について考えたきっかけは、プレパパ読書編として取り上げようと思っていた松田青子さん著「自分で名付ける」という本を読んだことです。
本書は著者の松田青子さんの育児の様子が描かれたエッセイです。松田さんは名字を変えず、事実婚としてパートナーさんと一緒に暮らしています。
印象的なエピソードがあるので紹介させていただきます。母子手帳をもらうシーンで松田さんは区役所の係の人から「名字が変わる予定があるなら名前を鉛筆で書いて」と言われたシーンです。その後お母さんに母子手帳を見せると、半ば呆れたように「今すぐボールペンで書き直したらいい」と言われます。以下本文引用です。
「言われてみればそうだなと私も思ったので、新刊にサインを書かせてもらう時などのために常備していた『なまえペン』という名前書きに特化したペンを机の引き出しから出し、区役所でほいほい書いた鉛筆の名前を消しゴムで消した。
そしてペンで自分の名前をもう一度書いたのだが、柔らかいクリーム色と黄色を基調とした表紙はつるつるした素材の紙が使われていたので、消しゴムをかけた部分だけが白くはげてしまい、名前の下でそこだけが目立つ。なので、見るたびに、いまだに、区役所での出来事を思い出す。名字が変わる予定があるかを聞かれたことと、だったら鉛筆で名前を書くように言われたことと。
どうして後になってこんなにこの出来事が気になるのだろうと考えてみたところ、もし結婚するのなら、名字を変えるのはおそらく女性側だろうという相手の考えが伝わってきたこと以上に、こちらに選択肢があるような話し方ではなかったからだと思い至った。
『お相手と結婚し、名字を変える予定があるのな、念の為鉛筆で書いておいてはどうですか?』と言う言い方をもし彼女がしていたならば、私が受けた印象も少し違った気がする。私の察しが悪かったせいもあるだろう。でも、自分の名字は場合によっては鉛筆書きになってしまうものなのだ、"仮"のものなのだ、という"発見"には虚をつかれるものがあった。厳密に言うと"仮"のものだと他者に思われているのだ、という方が近い。自分はそんなことないと思っているのに、周囲にあなたの体半分すけてますよ、と言われるような」
ではそもそも、日本ではいつから夫婦が同姓なのでしょうか。また他国ではどうなっているのでしょうか。
[名字ってなんなの?]
夫婦別姓に反対する意見としてよく「名字制度は日本の伝統で〜」と言われますが、日本の名字に関する制度の歴史を調べてみました。
・江戸時代以前
まず江戸時代まではそもそも平民は、一部の有力な平民を除き、氏の公的な使用は認められていませんでした。いわゆる武士には名字帯刀の特権があり、平民にはそれがないというものですね。
また名前は親が意味や思いを込めて付けるものでもなく、改名や名前の世襲もよくあることであったそうです。一生に一度も名前を変えなかった人はいないくらいだったとか。
確かにそんなイメージはありますよね。武家でも改名は当たり前。江戸時代以前は年齢や多分に合った名前を名乗ることが当然です。
豊臣秀吉を例にすると
足軽時代は「木下藤吉郎」
↓武家として出世したら織田家重臣の柴田勝家と丹羽長秀から一文字ずつ取って「羽柴秀吉」
↓信長の死後さらに出世して天皇から豊臣姓をもらい「豊臣秀吉」
現代とは名前に対する価値観が大きく異なりますね。
・名字制度の歴史
| 年代 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 明治3年(1870年) | 平民に氏の使用が許可される | |
| 明治8年(1875年) | 氏の使用が義務化される | |
| 明治9年(1876年) | 妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制) | |
| 明治31年(1898年) | 旧制民法成立 | 夫婦は家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制) |
| 昭和22年(1947年) | 改正民法成立 | 夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制) |
平民に氏を公的に名乗ることが許されたのは明治3年(1870年)のこと。明治維新後に平民にも氏を名乗る自由が与えられます。
続いて明治8年(1875年)、氏の使用が義務化されます。
これは兵籍取り調べのため、つまり後に起こる戦争の前準備として男性を管理する制度です。氏があったほうが全国レベルの管理はしやすいということでしょうか。
翌明治9年(1876年)、女性の氏は実家の氏と定めれらます。
この時点では夫婦別姓ということですが、どうやら当時から夫の氏を名乗る女性が増えていたようです。
そして明治31年(1898年)に施行された旧制民法に「夫婦は家を同じくすることにより同じ氏を称することとされる」 と記載されたことで、現在にまで至る夫婦同姓制度が法律で規定されました。
現在は昭和22年成立の改正民法により「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる」と規定されています。
歴史を振り返ってみると日本の夫婦同姓の歴史は実質的には1878年の氏を名乗ることが義務化されたあたりから続いていると考えられ、150年弱の歴史があるということになりますね。
まとめると、夫婦同姓制度はもともとは戦争のために作られた制度であり、歴史は150年くらい。とあれば現代から5〜6代前から続いていることで、伝統と言えなくもないですが、日本の歴史全体でみればさほど長くないとも感じられますね。絶妙な年数です。
僕が調べてみての感想としては意外と歴史短いのかなと思いました。少なくとも絶対的なものではないという印象です。
ちなみに民法とか出てきちゃってますが、世界で法律により夫婦同姓を強制しているのは実は日本だけです。なんかやばいですよね、それ。
次の章ではなんでそんなことになっているのかを考えることができました。少し。
言語学的な視点
名字の問題について調べていたところ、面白い論文を見つけました。英語圏と日本とで自己紹介する時にどう話すかを比較して、日本人が名字をどう考えているか研究したものです。
詳しい内容が知りたい方はお読みいただくとして、ざっくり概要を言いますと、日本人は集団的意識が強く、英語圏の人たちは個人的意識が強いのではないかということになります。
・日本人は集団的
日本人は「家族」や家族全体を意味する「家」という概念を重視する民族と言われています。
前の章で紹介した通り、確かに名字を持つことが公的に認められたのは明治に入ってからですが、それ以前にも名字は非公式ながら存在していましたし、「家」意識を強く持つ傾向がありました。
僕たちは何気なく「家族ぐるみ」「◯◯家の看板を背負う」などの言葉を使うし、葬儀においても「◯◯家式場」とするのが一般的で墓跡にも「〇〇家之墓」って書きます。
各個人は「家」という集団の中の一部であり、また「家」のみならず会社、学校、ひいては国家の一部という意識をしがちな民族のようです。
・英語圏は個人的
自己紹介の際、アメリカ人は自分の名前を真っ先に言います。しかし日本人の場合まず勤め先の名前を言い、場合によっては自分の名前は省略したりします。それで相手も満足します。話している人が誰かよりどの集団の人であるかが重要と考えからです。
これ、そうだなあと思いませんか?僕は深く納得しました。なぜなら映画で自分の名前を真っ先に言うアメリカ人の姿がすぐイメージできるうえ、僕は仕事の時インターホン押してまず会社名だけ言うからです(笑)。ていうか自分の名前を真っ先に言うことってありますか?僕はないです。
家族は個人が所属する最も身近な集団であると考えれば、英語圏の人たちと違い真っ先に名前を言うことはなく、所属集団である家の名、名字を優先させるのは自然ですよね。
日本で「僕はたけしです。」って挨拶されて「こんにちは、たけし!」とはならないですよね?え、で?ってなりますよね。それが集団的だということです。多分。
・日本人の「うち」と「そと」
そしてもう一つ重要な要素があります。それは名字で親密度を表せることです。
「家」を重んじる日本人には「うち」と「そと」をはっきり区別する民族でもあります。うちはうち、よそはよそって親に言われたことがあると思います。
そこでも名字は便利です。初対面の人、特別仲がいいわけじゃない人に対し名前で呼ぶのって失礼ですよね。なんか突然踏み込んできて怖い!ってなります。
これが僕らの感性です。「そと」の人が「うち」にずかずか入ってくる印象を受けるからです。
だから所属集団で呼ぶことってすごく便利です。名字には失礼な雰囲気が一切ありません。なぜならただの所属集団の名前に過ぎないから。
「うち」と「そと」を明確に分けたがる僕たちにとって、英語圏の人たちより名字の重要性は高いのかもしれません。
そんな僕も外国人と話すときは名前で呼ぶし、名前(ニックネーム)で呼ばれます。それは自然な感じです。
よく考えると変ですよね、日本人と話す時だけ突然名前で呼ばれると嫌な感じがするの。文化って不思議。
[まとめ]
今回色々調べて名字について考えてきましたが歴史や文化が絡んできていてとても面白かったです。
日本人が集団的生き物として他国(少なくとも英語圏)より名字を大事にしているという話にはある程度納得できました。
またなおさらのこと、自分のアイデンティティである名字を変えたくない人がいたっていいと思うようになりました。この考え方は結婚して名字を変えることで同じ「家」として集団になれるという考えと同じように尊重されるべきと思います。
僕は別に別姓が絶対いいと言っているわけではありません。
僕はくるみ🐿️と同じ名字になって嬉しかったです。まさに日本人的感性の下でそう思いました。でも人それぞれに事情や思いがああるわけですよね?
だから、選べたらいいと思います。別々でもいいし、一緒でもいいし。
名字を一緒にしなくなったからと言って「家」制度が即崩壊とは思わないですし。何も名字だけが集団を規定するものじゃないでしょ?住む場所とか信じているものとか、なんでもまとめ方はあるわけですし。
頑なに名字を絶対一緒にしろ、というのは短絡的じゃないかな。
「夫婦同姓は日本の伝統」ってほど歴史が深いわけでもないですし、日本の歴史にも現代の世界にも名字が違う夫婦が存在し、問題なく繁栄してきました。
それなら名字を変えることで、変えなければならないことで大変な思いをする人、不都合な人が生じないように選べればいいと思うんです。
それが現状、実質的に女性の負担増となっているからまずいと思うんです。選べれば回避したい人は回避できる問題になります。それで良くないですか?
長文になりましたが、読んでくださって本当にありがとうございました!みなさんの意見が聞きたいです。
名字について、夫婦別姓についてあなたはどう思いますか?

![プレパパブログ[選択的夫婦別姓編]松田青子著「自分で名付ける」を読んで〜夫目線で妻の妊娠について〜](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5xXpmIF8mjz-oFGgysoQcHySsZRbqNf0p2ncKfyhPYznLTg990fwSzwzMTGwHmq4YeeZ0PYn0uoMVyrI-uPV4dvoyYHsAYfskPY77ZUUOW1yxO-roZIycHhbWi96GyYJCuLkkEO-lOHCQdr5Gn_CSK6n16lM8JTf_aM__gwbJ_AEdqP3fJm3LzG4rYkuT/s1600-rw/IMG_1674.png)

![[ダブル育休1年のメリット]住民税・保育園料が無料になる?](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-odSMp8R4QmRAdXr6ylSZO6id0g3KCWR4wDa4BJWCQqwvGemfMwyseOvFa40s5p1ju6FJUFZkLfAfh1k3FIVqruAGusulInba02CN5ojLmaFdZ6pRoVbVLSt9sw7-_plP2KKdrTYdb7T3KVJsepLpDNqfXVgBKYpOcz-lm2HEgnyvjOGRXptJmis7EJZe/s1600-rw/IMG_5265.png)